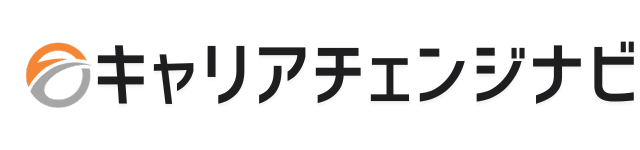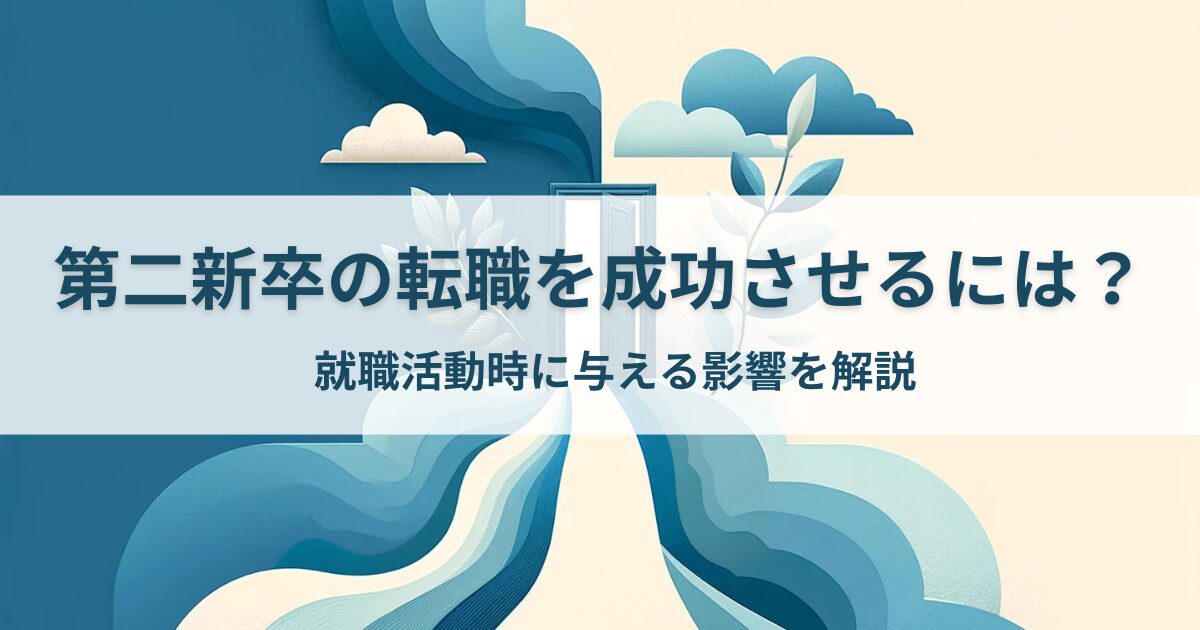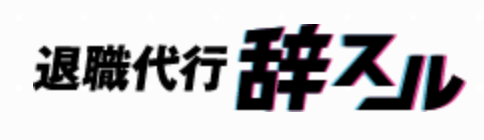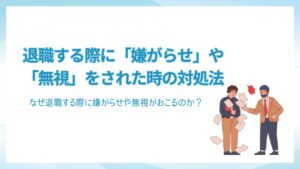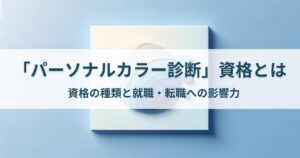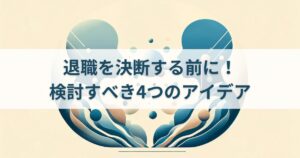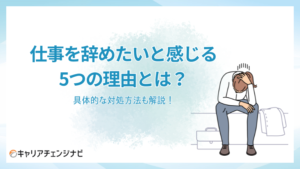最初に就職した職場があわなくて離職したんだけど、「第二新卒」としての就職活動って、どうやればいいの?
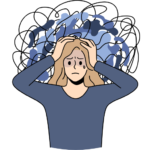
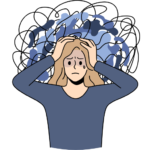
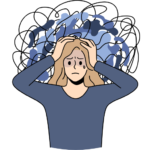
第二新卒の就職活動って、新卒のときと何が違うんですか?
この記事では、第二新卒の就職活動について、その特徴や新卒での就職との違いについて紹介していきます。
- そもそも「第二新卒」とはどういうもので、「新卒」と何が違うのか?
- 「第二新卒」に公務員が人気の理由
そもそも第二新卒って?
日本の就職文化において、大学・専門学校等を卒業後に初めての就職を果たすことを「新卒」と呼びます。
「第二新卒」は、就職を経験した後に離職し、再び新たな職場で働く若手社会人を指す言葉です。
第二新卒と普通の新卒の違い
第二新卒と普通の新卒との違いは、主に以下の点が挙げられます。
- 就職経験の有無
- 離職経験の有無
- 職務経験とスキルの違い
- 求められるポジションと条件
- 採用のハードル
これらの違いにより、第二新卒と普通の新卒は、就職活動やキャリアの展望において異なる状況・課題を抱えることがあります。
就職経験の有無
まずは、就職経験の有無です。
第二新卒は、すでに一度就職した経験がありますが、普通の新卒は初めての就職をする人を指します。
離職経験の有無
次に、離職経験の有無が異なります。
第二新卒は、新卒として就職後に一度離職した後で再び新しい職場を探す人を指します。
一方で、普通の新卒は初めての職場で働く人を指しますので、離職経験はありません。
職務経験とスキルの違い
第三に、職務経験とスキルの違いがあります。
第二新卒は、前職で得た経験やスキルを持って新しい職場に入ることが多いです。一方で、普通の新卒はまっさらな状態からスタートするため、経験やスキルに差があります。
求められるポジションと条件
第四に、求められるポジションと条件が異なります。
第二新卒は、前職での経験を活かして新しいポジションを探すことが一般的ですが、普通の新卒は未経験からのスタートなので、求められるポジションや条件が異なることがあります。
採用のハードル
最後に、採用のハードルに違いがあります。
第二新卒は、前回の離職理由や職歴の短さから、採用側からキャリアの安定性に疑念を抱かれることがある一方、普通の新卒は特定の企業とのマッチングを重視する傾向があります。
「第二新卒」が就職活動時に与える影響
「第二新卒は、就職活動時に低い評価になるのでは?」と心配している方も多いでしょう。
しかし、第二新卒が転職活動時に低い評価になるかどうかは、一概には言えません。
評価は個々の状況や企業のポリシー、求人市場の状況によって異なりますが、以下のような要因が、第二新卒の評価に影響を与えることがあります。
- 離職理由とキャリアの安定性
- 前職のスキルの評価
- 成長意欲とポテンシャル
- 適切なポジションへのマッチング
- 企業の文化やポリシー
- 景気と転職市場の変動
離職理由とキャリアの安定性
まず、離職理由とキャリアの安定性です。
第二新卒の場合、前回の離職理由や職歴の短さから、採用側からはキャリアの安定性に疑念を抱かれることがあるかもしれません。
これが採用の際のハードルとなることがあります。
特に、複数回の転職歴があると、どうしてもキャリアの安定性に対して不安が生じることがあります。
前職のスキルの評価
第二新卒は既に一度の就職経験があるため、その間に得たスキルや経験を新たな職場でどう活かすかが問われます。
そのため、前職でのスキルや経験が、新しい職場でどれだけ役立つかによって評価が変わることがあります。
前回の経験を活かせる場合、その点はプラスとなるでしょう。
成長意欲とポテンシャル
また、成長意欲とポテンシャルも評価の要因です。
第二新卒の場合、前回の離職を経て成長意欲や新たな挑戦の姿勢を評価することがあります。これによって、過去の経歴以上に将来の成長や貢献度が重視されることがあります。
また、第二新卒の場合、初めての新卒と比べて年齢が若干上がっていることが一般的です。
これにより、同じ職場で新卒採用と同じ条件で競争することが難しい場合があります。
とはいえ、第二新卒でも前職で得た経験やスキル、成長意欲を適切にアピールし、適切な職場を選ぶことで、高い評価を受けることは十分に可能です。
適切なポジションへのマッチング
さらに、適切なポジションへのマッチングも重要です。
前職での経験を活かせるポジションを選び、自身の強みを最大限にアピールできるかが採用時の評価に影響します。
適切なマッチングができれば、評価も高まる可能性があります。
しかし、そのマッチングが難しいこともあり、その場合は、新たな成長も見据えた選択が求められます。
企業の文化やポリシー
転職しようとする企業の文化やポリシーも、第二新卒の転職活動に大きな影響を与えます。
たとえば、多様な経歴を歓迎する企業もあれば、安定した経歴を求める企業も存在します。
景気と転職市場の変動
最後に、第二新卒の転職活動は、新卒採用よりも顕著に求人市場の動向や需要に影響を受けることがあります。
景気や業界の状況によって求人の数や内容が変動し、その影響を受けやすいのが特徴です。
第二新卒の就職先として公務員が人気!
第二新卒の中には、新たな就職先として、公務員を選ぶ人が多いです。
その理由は次のようなものです。
- 公務員の採用年齢制限が比較的広い
- 安定した給与や福利厚生
- 社会的な信頼感や責任感、地域社会への貢献度
理由1:公務員の採用年齢制限が比較的広い
まずは、公務員の採用年齢制限が比較的広いことが挙げられます。
公務員の中には、30歳以上や35歳以上などの年齢であっても採用を受け入れる自治体や機関があり、この点が、第二新卒の方々にとって魅力的な選択肢となっている要因です。
理由2:安定した給与や福利厚生
公務員の仕事は安定した給与や福利厚生、長期的なキャリアプランの確立といった特徴があり、一度の転職で長期的な安定を求める方にとって魅力的です。
理由3:社会的な信頼感や責任感、地域社会への貢献度
また、公務員としての社会的な信頼感や責任感、地域社会への貢献度も魅力の一つとされています。
公務員を目指す際の注意点
ただし、公務員試験は競争率が高く、学習や準備が必要です。
また、適性や志向性に合った職種を見つけることも重要です。
また、中央省庁の国家公務員や、県庁・市役所の内部管理部門では、過酷な長時間労働を余儀なくされる事例も多々ありますので、「楽したい」という人には向いていません。
年齢制限が広いとはいえ、適切な職種や地域を見つけて挑戦することが成功のカギとなるでしょう。
まとめ
この記事では「第二新卒の転職を成功させるには?」について解説しました。
記事の内容をまとめます。
- 前職での経験やスキルを活かせるポジションを見つけることが大切
- 過去の離職経験から得た成長意欲や新たな挑戦の姿勢をアピールする
- 公務員など、年齢制限の広い職種にも注目
キャリア転換をする際は、情報収集と準備が欠かせません。
第二新卒の方は、一度は就職経験があるからこそ、新たなステージでの活躍が期待されています。求人市場の動向や入社試験の内容を把握することで、自信を持って挑戦しましょう。
転職は大きな挑戦の連続になるかもしれませんが、ポジティブな姿勢を持ち続けることが大切です。
失敗や難局も成長のチャンスと捉えて、前向きに進んでいきましょう。